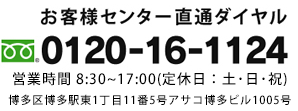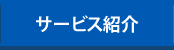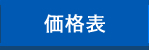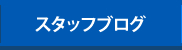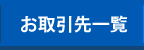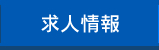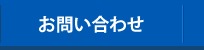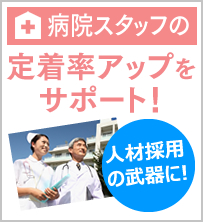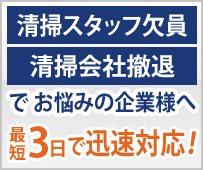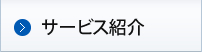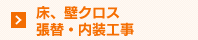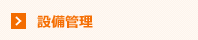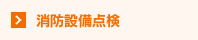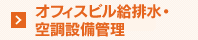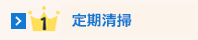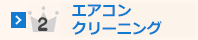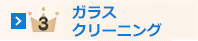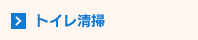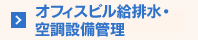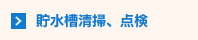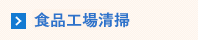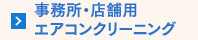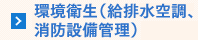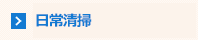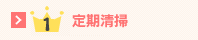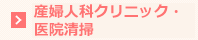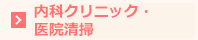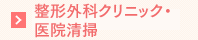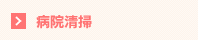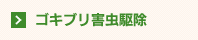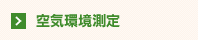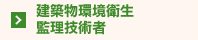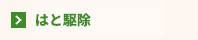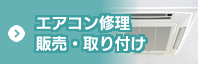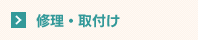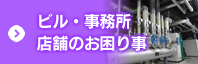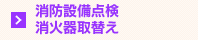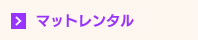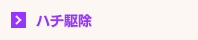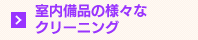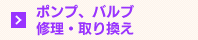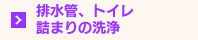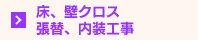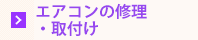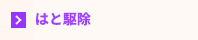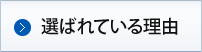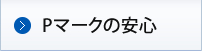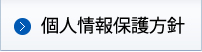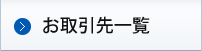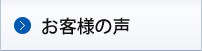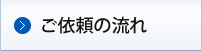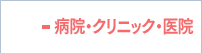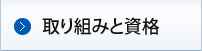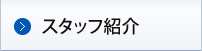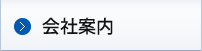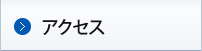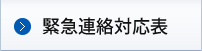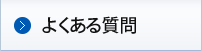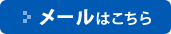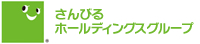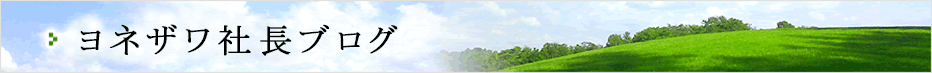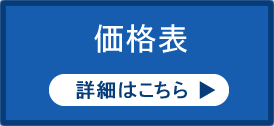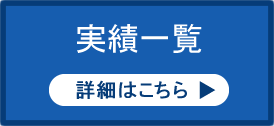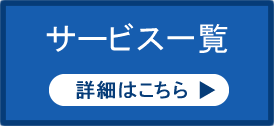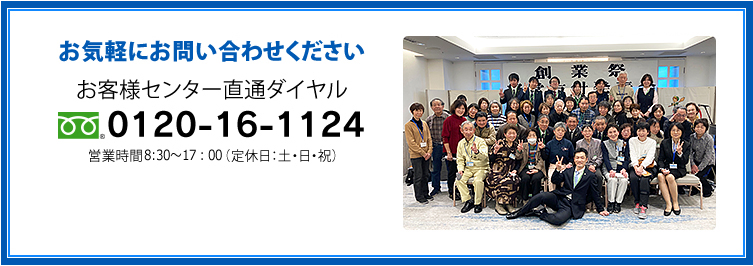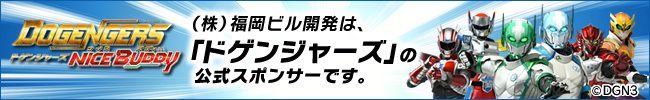選手宣誓
宣誓
いまありて未来の扉を開く。
いまありて時代も連なり始める。
1924年、第1回全国選抜中等学校野球大会として春の選抜大会が開催されました。
あの日から100年。
我々、高校野球球児の甲子園大会に対する夢や憧れは、長年の時を超えても変わることなく、いまもなお、夢舞台であり続けています。
夢にまで見たここ甲子園に立ち、これまでの先輩方が築き上げられた歴史と伝統の重さを身に染みて感じています。
同時に私たちは唯一無二の仲間とともに大好きな野球に打ち込める今に喜びをかみしめています。
今年の元日に能登半島沖で大きな地震が発生しました。家族団らんと過ごしている中での激しい揺れに私たちは恐怖と深い悲しみに襲われました。
被災地では現在も苦しみと困難の多い生活を余技なくされています。
私たちにできることは目の前の白球をがむしゃらに追い続けること、そして全力で野球を楽しむことです。
今日から始まる選抜大会を、次の100年に向けた新たな一歩とするべく、全身全霊をかけて戦い抜くことを誓います。
きょうまでの100年、きょうからの100年。
令和6年3月18日、選手代表、青森山田高等学校、主将、橋場公祐
100年も続く夢舞台
さぁ、球児に感動をいただきます
そしてそれを力に変え、全力で事業を進めていきます!
大手提携
今日の話題
なんと日産とホンダがEV分野で提携へ
昔まではライバルが今は友
駆動装置の部品の共通化や調達連携、また車載ソフトも協業へ
国内の2位と3位が提携を進めれば自動車業界も発展するのはないでしょうか
しかし今のところ資本提携はないとのこと
EV市場、車メーカー以外の参入もあり大きく変化しています
その中で日産とホンダの提携は意味がわかるような気がします
世界に目を向けてみると、EV販売台数はトヨタ10万台、日産が14万台、ホンダは1万9千台
一方テスラは140万台、中国のBYDが157万台と日本メーカーは大きく水をあけられています
この2社の提携により技術力、販売力さらにはコスト競争が高めることできるのではと期待しています
QR決済
QRコードは、1994年に日本のデンソーウェーブが開発
最初は自動車部品の管理のために作られましたが、今では世界中で広く使われるようになっています
現座ASEAN地域では、異なる国や地域でのQRコードの使い方が増えているようですが
2025年度をめどに国境に関係なくQR決済で支払いができるようになるようです
そうなれば旅行者の利便性の向上、またビジネスや教育など、さまざまな場面で活用が可能になるのでではないでしょうか
また日本発のQRコード
中国への対抗でASEANへの影響力を高めることもできるとのことです
海外で買い物するとき
食事をするとき
クレカ以外の決済方法が増えれば大変ありがたいですね
日本ではキャッシュレスといえばクレカ
しかしながらアジアではQRコード利用の比率が高いとのこと
日本発の技術でアジアを世界をより便利にしてほしいと思います
民間ロケット!
宇宙事業会社のスペースワンが打ち上げた小型ロケット「カイロス」が
残念ながら自立破壊で目標を達成できませんでした
この民間会社の社長が記者会見で放った言葉にとても勇気をいただけました
「スペースワンとしては、失敗という言葉は使いません。
なぜかというと、一つ一つの試みの中に、新しいデータがあり、経験があり、そうしたものは
すべて今後、新しい挑戦に向けての糧と考えている。
私どもとしては、前に進んでいくので、ぜひ応援していただければありがたい」
諦めない心
このロケット打ち上げは必ず成功します
そんな気概をいただきました
がんばれスペースワン!
がんばれカイロス!
男性育休について
政府はこのほど男性育休の取得を促すため法改正を閣議決定したようです
男性は取得日数も少なく日数も短い
企業には情報開示の義務化や体制を整備するといったことを促すようです
2023年の出生数は76万人
2015年は100万人が20万人も減った
今までは専業主婦が家事や育児をしていたが専業主婦は3割を割り、共働きが主流になっています
共働きでの家事育児時間は女性が6時間半、男性が約2時間といまだに女性が家事育児がするのが普通です
そんな中で伊藤忠商事は4月から男性社員の育児休暇取得を必須としたり
イオンは子供が1歳になるまでの育児取得休暇中、手取り額を休業前と同水準にする
いずれにせよ仕事の育児の両立は大変であり
大企業が先行し、男性の家事育児参加を普通の世の中にしてもらいたいと思います
利益トップ企業の変化
今日の話題
32業種でコロナ前と現在で業界地図が一変
上位に浮上する企業はインフレが進む中でも強みの商品やサービスの値上げを浸透させている企業
価値に見合った価格へ
そして事業構造改革
売れない事業から売れる事業へ
ソニーであればエレクトロニクス事業をテコ入れしつつゲームや音楽などのエンターテインメント事業に力を注いで電機機器のトップへ
モノからコトへ
時代は動いていますね
わが社も同様に
モノからコトへ、そしてトキへ
いよいよあと20日で第57期が終わります
新たな扉を開けていきたいと思います
3.11
震災から11年が経過しました
私たちは、そのときの被災者の方々の苦しみや悲しみを決して忘れてはなりません
震災は、私たちに自然の力の偉大さを改めて思い起こさせる出来事であり、また、防災や備えの大切さも教えてくれる出来事でもありました
被災地では、復興が進みながらもなお課題が山積しています
私たち一人ひとりが、日常生活の中で少しの工夫や備えをすることで、災害に備えることができます
非常用品の準備や避難経路の確認、災害時の連絡手段の確保など、普段から意識しておくことが重要です
また、震災からの復興を支援するためには、被災地を訪れたり、支援活動に参加したりすることも有効です
被災地の方々との交流を通じて、被災地の現状や課題を理解し、支援の手を差し伸べることができます
震災からの復興はまだまだ続く道のりですが、私たちの力を合わせて支援し、被災地の方々と共に歩んでいきましょう
被災地の方々への思いやりと支援を忘れず、震災の教訓を生かして、安全で安心な社会を築いていきましょう
被災された方からのメッセージ
「いつまで経ってもこのことを忘れないでほしい」
がんばれ東北!
がんばれ東日本!
がんばれの能登半島!
たくさんの人でした
今日はお取引が開始したヤマタさんのネーミングライツされる運動公園に行きました
山陰でここまで大きな敷地の運動公園は見たことがありません
素晴らしい施設です
運動場、体育館、テニスコート、サッカー場、野球場、そして遊具
一日いても飽きないかもしれません
そして敷地内にはカフェ
これも山陰では見かけたことがありません
やはり運動は良いですね
以前はマラソンをしていた関係で、このような環境になると無性に走りたくなるのは気のせいでしょうか
ランニングは正しい姿勢やフォームが重要と思います
とくに有酸素運動をする際には、正しい姿勢を保つことで効果的に体を動かすことができます
背筋を伸ばし、肩を後ろに引くような姿勢を心掛ける
これにより、腰や膝への負担を減らし、効率な運動が可能
そして、無理しないこと
以前はこのようなことを考えながら身体を動かしていました
走るのをやめて2年以上
最近はスタンディングデスクで立って仕事
春になれば走りますか
時間があればですが
7割減
春の選抜が18日から開幕
熱戦が期待されている裏で、ピーク時は18万人が25年後には5.2万人とのことで
高校年代の人口の減り方より高校球児の減り方が非常に速いとの予測です
そかも7割も減る予測
最近は丸刈りが26.4%
休日の練習時間は5時以上は50%
毎日の練習は3%とのことで以前とは様変わりをしています
そして高校ではチームの人数が揃わなく合同チームが増えているとのこと
世の中も大きく流れが変わってきました
複数校が協力し小学校向けの野球教室を開催したり
選手の自主性にまかせた運営等々
そして部活動を地域クラブへの移行や指導者を地域の人材を活用したり
ICTの導入など
人口が減り、子供の数も減り学校の部活動も大きく変化をしなければなりません
スポーツの面白さ
形は変わっても子どもたちには味わってもらいたいと思います